JOYCE.NG×レイナ・オガワ・クラーク Special Interview


今秋5周年を迎え、大いに盛り上がりを見せる心斎橋PARCO。ここから先へのさらなる進化を見据え、クリエイティブでも新たなチャレンジを試みた。大阪の街を舞台に撮影が行われたキャンペーンビジュアルは、フォトグラファーJOYCE.NG(ジョイス・ウング)と、スタイリストのレイナ・オガワ・クラークによるスペシャルタッグが実現。被写体には、国内外のランウェイで注目を集めるモデルMonaを起用し、「前兆」というコンセプトを体現した力強いグラフィック広告、そして、突然の風に導かれるシネマティックな映像が完成。ロンドンにも拠点を持ち、かねてより親交のあるクリエイターの2人に、撮影の裏側と、互いのクリエイションについて話を聞いた。
- Edit & Text
- Chikei Hara
- Photo
- Mami Nakashima
- Edit. RCKT
- Rocket Company*
―今回の撮影はいかがでしたか?雰囲気やクルーの印象について聞かせてください。
ジョイス
とても理想的なクルーで良い現場でした。すべてが自然に噛み合っていて、スムーズに進んだのはプロダクションがしっかりしていたからです。みんなが自分の役割を超えて取り組んでくれて、想像以上のクオリティになりました。
アジアで仕事をするときは、人々があまり打算的じゃないというか、自分の担当はここまでと線を引いて動くのではなく、互いが謙虚な姿勢をもちながらも、チームの中で足りない面を支え合う印象があります。
ちなみに、今回が初めての日本での撮影でした。大阪には2回訪れたことがありますが、撮影をしたのは今回が初めてです。
―大阪にはモダンなものと昔ながらの価値が共存する文化があって、自然と一致団結するチーム性が根づいていますよね。撮影の中でもそういう空気を感じたりしましたか?
ReIna
今回は企画からクリエイティブディレクションとして参加し、心斎橋PARCO5周年という機会に、大阪の街そのものにフォーカスした撮影を計画しました。
テーマが「前兆」だったので、風というアイディアを取り入れました。また大阪についていろいろリサーチを進めるなかで、食い倒れ人形や大阪市のマークに使われている赤と青の色彩がとても印象的だったんです。そこでスタイリングにも赤や青のトーンを取り入れて組み立てました。

―今回のスタイリングでは、インディペンデントな日本のブランドとヴィンテージアイテムをミックスした表現が印象的でした。どのように選定されたのでしょうか?
ReIna
この企画をパルコと構想する中で、最初に出てきた話題が「日本の若手ブランドを取り上げたい」というものでした。その言葉を聞いて、とても嬉しかったんです。というのも、私にはジャーナリストをしているパートナーがいて、彼と一緒に『Vogue Runway』向けの記事を書くために、多くのデザイナーへインタビューを行ってきました。そうした経験を通じて、東京のファッションシーンの盛り上がりを私自身も強く感じていたからです。
そこで今回は、いま本当に勢いのあるブランドであるpillingsとHARUNOBUMURATAを取り入れました。さらにKenzoなど、日本を代表するレジェンドブランドのヴィンテージも加えています。私のスタイルとしても一貫して「日本のブランドを代表する」ことを意識しており、新しいものと伝統をうまく掛け合わせて表現しました。今回も振り返ってみると、「古き良きものとモダンファッション」をテーマにしたスタイリングに仕上がったと感じています。
―ロケーションも大阪の過去と現在を象徴するような場所ですね。ジョイスさんは今回の撮影をどう感じましたか?
ジョイス
以前大阪に来たときには、こうしたボザール様式の建築の中に入った記憶がありませんでした。実際に足を踏み入れてみると、とても強く「上海みたいだな」と感じたんです。上海にはフレンチ・ボザール様式の建築がありますが、それに近い雰囲気がありつつ、よりコンパクトでまるでおもちゃの模型のようにも見える。私たちを過去に導くような雰囲気が、今回のスタイリングのコンセプトにぴったり合っていました。今回は大阪を拠点にしている人たちと直接仕事をしたわけではありませんが、古い建物に囲まれて暮らす感覚にはとても惹かれました。
それに、水のある都市ってやっぱりいいですよね。街の中を川が流れていて、車で移動しているときにはお城の前を通ったりもして。日常の中に自然と歴史が息づいていて、古いものと新しいものを混ぜ合わせる感覚が、この街の人々の精神に根づいているのだと思います。こうした建物に入ると、歴史と向き合わされるから自然と立ち止まって、少しスローダウンする気持ちになります。今回、ムービーのあるシーンを中之島図書館で撮影したのですが、開館前に撮影を終えて外に出たら、入館を待つ人が大勢いて。きっと勉強や仕事のために日常的に利用されている風景なのでしょうけれど、モダンなカフェとしてサービスが提供されるのではなく、タイムカプセルが街にあるのは本当に素晴らしいことだと思いました。

―日本文化の特異性は、静かで落ち着いた禅の精神性にあると感じます。これまで各国を訪れてきた中で、日本特有だと感じるものはありましたか?
ジョイス
日本に対してリスペクトしているのは、「これが私たちの伝統です」と胸を張って守ろうとする姿勢にあります。もちろん、日本にもグローバルに開かれている部分がありますが、ロンドンに住み、香港で育った私からすると、グローバルな都市はどんどん同じ表情になっていくことはとても悲しいんです。
豊かになりつつある他のアジアの国々でも、多くは海外に留学した裕福な学生が海外の生活スタイルを輸入して、そのまま街をつくろうとする。それって同じものをただコピーしているだけで、それが本当の豊かさにつながるとは思えません。むやみに新しくする必要はない。守るべきものが確かにあって、それを残すことこそが豊かさを生むのだと思います。
西洋では、こうした態度が閉鎖的、保守的と誤解されがちなのも残念ですね。自分たちの文化をごっそり混ぜ合わせることばかり考えてしまうと、自分の言葉や生活様式をどうやって守るのか、いう生活の地域性への問いが置き去りにされてしまうのではないでしょうか。

―Reinaさんとジョイスさんは、それぞれクリエイティブのオリジナリティや独立した視点が際立っているように思いますが、お互いのクリエーションをどう見ていますか?
Reina
ジョイスの写真って、必ずストーリーがあるんです。単なるモード写真やポートレートじゃなくて、何かが起きた前後まで想像できるようなシーンを切り取っている。そうしたストーリーテリングの感覚にユーモアもあって、今回の世界観にもぴったりだと思いました。それがあなたの作品の好きなところ。そして、パルコとの相性の良さを感じて、最初に「一緒にやりたい」と思った大きな理由でもあります。
ジョイス
そうそう、それがあるから私は映像も好きなんです。私の写真には「前」と「後」があるから。Reinaのスタイリングは、常にフェミニンなんだけど、シリアスすぎないところが好きです。レイヤードしていても軽やかに見えるし、実用性があって親しみやすい。けれどどこかにちょっと違うなと思わせるような挑戦に違和感はなくて、そこに共鳴するんです。スタイリングの問いも、決してギミック的に押しつけられるものではなく、とても本質的な提案されているのがいいんですよね。
Reina
受け取ってもいいし、受け取らなくてもいい、っていう提案ね(笑)
ジョイス
そう、真剣ではあるけれど硬すぎない。洗練されてるけど、気取ってないバランスが良い。

―クリエイションをする上で大切にしていることは?
Reina
海外に住んでいたこともありますが、日本で育っていた頃はヨーロッパやアメリカに憧れていて、ずっと「かっこいい」と思っていました。おそらく今も多くの日本人がそう感じていると思います。 でも実際にヨーロッパに渡って、日本を外から見つめ直すようになったとき、周囲の人たちが日本文化に強いリスペクトを抱いているのを目の当たりにして、自分は日本のことを何も知らなかったと気づかされたんです。日本人として、日本のアートとは何かを理解していなかったという問題を突きつけられたように思いました。
それから日本文化の勉強やリサーチを始めて、日本には驚くほど多くの魅力があると分かりました。だから私はスタイリングをするとき、常に日本のファッションやクリエイティブな要素をベースに違いを引き出しつつ、そこにヨーロッパの感覚を少しミックスするスタイルを意識しています。私にとって大切なのは、そうやって「文化を掛け合わせながら新しいものを生み出すこと」なんです。
―自身のアイデンティティに触れたのは、やはり海外に行って帰ってきた経験が大きかったですか?
Reina
ちょうどコロナの時期にロンドンに住んでいたのですが、厳しいロックダウンの影響で、みんなが仕事を失うような状況が続いていました。そんなステイホームの時間に、何か新しいことを始めようと思ったんです。
そこでパートナーと一緒に、日本のアートやカルチャーをリサーチして紹介するアカウントを趣味で立ち上げて、これまで知らなかった日本のことを改めて学ぶことができたんです。振り返ると、あのコロナの時間が今のクリエイションの基盤をつくってくれた、とても大切な経験だったと思っています。
ジョイス
私も似ているかも。作品のテーマとまでは言えないけれど、私の場合は海外に出てから、生き方として自分の文化と改めてつながらなければと強く思うようになりました。
生まれ育った香港はとてもグローバルな街で、街の至るところに広告があったので、子どもの頃から商業性というものが身近に根深く存在していて、違和感を感じたことがありませんでした。だからこそ、私の作品には大きな使命があるというよりも、むしろ子どもの頃の記憶を掘り下げている部分が大きいと思います。
商業イメージとファッションイメージは、前者が大衆向けで後者がニッチで洗練されているものとしてしばしば区別される。だけど無意識のうちに、この境界線を打ち破りたいと私は願っています。互いに排他的でないイメージを創り出すには、はるかに多くの知性が必要になるでしょう。
つまり、ファッションイメージに対して過剰に神経質にならず、もっと自由でいたいんです。

―創作において「新しいもの」を見つけるのは、すでに難しい時代ですよね。ファッションでもアートでも、ほとんどすべてのアイディアが出尽くしてしまっている中で、考え方や作品づくりにおいて転機のような出来事はありましたか?
ジョイス
「There’s nothing new under the sun.(=新しいものなんて、もう存在しない)」と何度も思い知らされますね。
ただ、面白いエピソードがあって。若いフォトグラファーの友人が自主プロジェクトで「ケンカした雰囲気のカップルがお互いの服を窓から投げ捨てる」シーンを撮りたいと言ってきたんです。そこで一年前くらいに、ちょっと変わった私の持ち物や服をたくさん貸してあげたんです。
そして先日、その友人と一緒にテート美術館で開催されていたLeigh Boweryの展示を見に行ったとき、とても似たアイディアが展示されていたんです。しかもそれは1990年に東京のPARCOで開催された展覧会のための出品作の一部だったそうで、それにも驚きました-。彼女はその作品を事前に知っていたわけではなかったので、本当に奇妙な偶然でした。結局のところ、何も新しいものはないという言説を確かにするような体験でした。
ちょっと陳腐に聞こえるかもしれないけれど、私たちは一見バラバラに生きているように見えても、同時代を生きていない誰かと同じことを想像しながら、考えたりしているんですよね。
ジョイス
最近感じてる“新しさ”って、むしろ「回帰」なのかもしれないね。 いまのイメージメイキングにはすごくポリティカルな空気があって、大きなメッセージや社会的テーマを背負わなければならないような雰囲気があります。でも、もっと小さなアイデアとか、やってみたいから作るという純粋な欲望に立ち返ってもいいんじゃないかなと思うんです。コミュニティにどう受け取られるかではなく、ただ作りたいから作るという気持ちにこそ、新しさがあると感じています。
Reina
ちなみに今回のシューティングでは、参考資料としてパルコの過去の広告をたくさんリサーチしました。そのなかで面白い発見もいくつかあったんです。80年代、90年代のパルコの広告に心を打たれるのは、インパクトと個性があって、強く記憶に残るからだと思います。たとえば、スーツ姿の内田裕也さんが水中を泳いでいる広告なんて、一見すると意味が分からないけれど、しっかりとストーリー性があって面白い。今回パルコのクリエイティブに関われたことは本当に嬉しかったし、過去の広告を見ながらもっと自分の表現を広げていきたいと思いました。
ただ、ここまで奇抜なクリエーションをするのは簡単ではありません。いまの時代はどうしてもSNSやオーディエンスの反応を気にしすぎてしまう傾向があるので、だからこそもっと大胆にチャレンジしたいですね。
ジョイス
私もパルコのすごさは以前から知っていましたが、今も継続して成功しているのは、クリエイターに信頼を置いているからだと思います。
デパートにとって商品やサービスの質は明らかに大切ですが、お客さんはすでに消費の仕組みを理解してるのでそれだけでは差別化できない。大切なのはライフスタイルの提案や価値観の表現を通じて、どうお客さんに伝えるかという点なんです。
そこで問われるのは、世界をどう見て、どう解釈して、それをどう届けるか。パルコは常にフレッシュで、定義に縛られすぎない。誰にでも解釈の余地を開き、ビジュアルコミュニケーションの定義を狭く捉えていない。いつも解釈の幅があって、とてもオープンなんです。商業性に縛らせておらずあらゆる探求が許されている、そこがパルコの魅力なんです。
Reina
それって簡単なようで、実はなかなかできないことだよね。

Joyce NG(ジョイス・ウング)
フォトグラファー
香港で育ち、現在はロンドンを拠点に活動するフォトグラファー、ディレクター、クリエイティブディレクター。幼少期を街のモールを歩き回りながら、多様な人々の営みを観察して過ごす。この経験は、ストリートキャスティングへの関心へとつながり、フォトグラファーとしてのキャリアの礎となった。現在も、ジョイスの青春時代の経験は、写真作品に色濃く反映され、遊び心と映画的な手法を織り交ぜた作品では、香港特有の混沌とした美しさや、香港コメディ映画のジャンル「無厘頭(ムーライタウ/もとは “with no source”)」に見られるスラップスティックなユーモアを表現。新しい人々と出会うことへの好奇心を持ち、被写体のありのままの姿・感情を引き出すことが魅力。作品はファッションブランドや出版物で紹介され、近年のコラボレーションには、National Geographic、Frieze Week London Magazine、Vogue+、W Magazine、Buffalo Zine、Dazed、Luncheon、Marc Jacobs、Burberry、Adidas、OVH、Dover Street Marketなどがある。
@joyceszeng
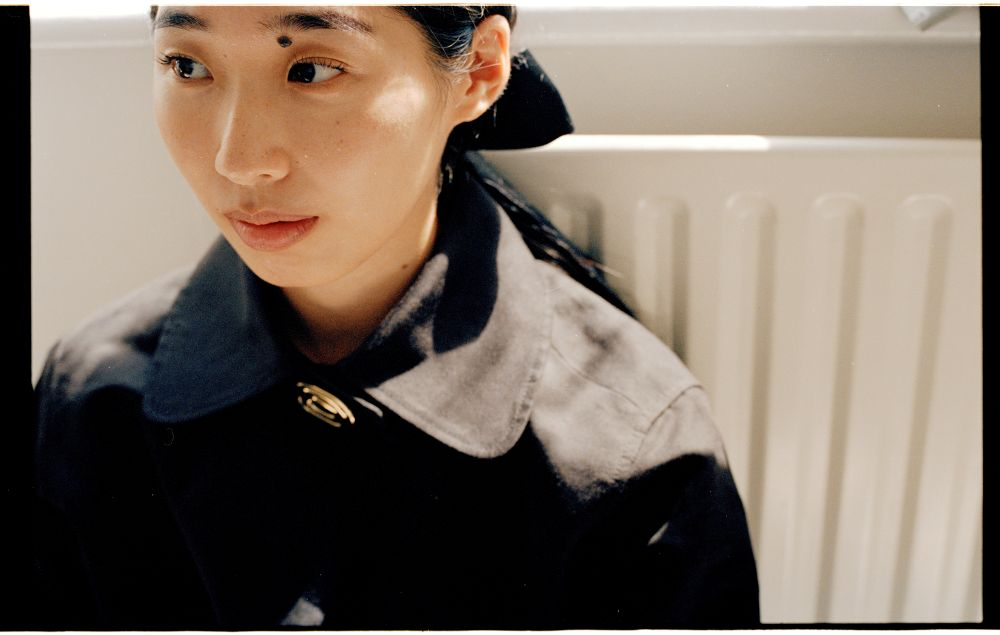
レイナ・オガワ・クラーク
スタイリスト/クリエイティブディレクター
スタイリストBrian molloyのアシスタントをしながらスタイリングを学び、フランスへ渡仏、その後ロンドンで活動し独立後は、東京とロンドンを拠点に活動。国際的な視点を生かし、広告やエディトリアル、ブランドキャンペーンなど幅広い分野で活躍。AURALEE、DIOR、ISSEY MIYAKE などのプロジェクトに携わり、洗練された感性と柔軟なスタイリングで注目を集めている。
@reinaogawaclarke
